従二位家隆
小倉百人一首 098 |
風そよぐ ならの小川の 夕暮は みそぎぞ夏の しるしなりける |
| かぜそよぐ ならのをがはの ゆふぐれは みそぎぞなつの しるしなりける |
従二位家隆 |
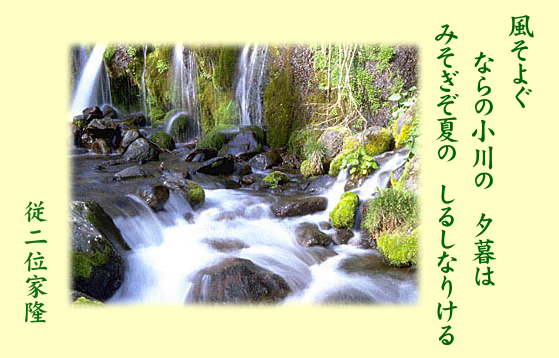 |
| 読み かぜそよぐ ならのをがはの ゆふぐれは みそぎぞなつの しるしなりける 現代意訳 風がそよそよと楢(なら)の葉を吹きわたるこのならの小川の夕方は、(もうすっかりと秋のような気配だが) 川辺の禊祓(みそぎはらい)を見ると、まだ夏であるのだなぁ。 ※ならの小川 / 京都市にある上賀茂神社の前を流れる御手洗川。「楢」にもかけている ※みそぎぞ / 「みそぎ」は「禊祓(みそぎはらい)」のことで、この場合は六月に行われる「六月祓(みなづきばらえ)」のこと。川の水などで身を清め、穢れを払い落とす行事で、「ぞ」は強調の係助詞 季節 夏 出典 「新勅撰集」 解説 従二位家隆(じゅうにいいえたか・保元3年~嘉禎3年 / 1158~1237年)は権中納言 藤原光隆の次男で、嘉禎元年(1235年)、七十八才のときに従二位になっています。 家隆は藤原俊成に歌を学び、定家とならぶ優れた歌人として知られています。 「新古今集」の撰者でもあり、歌合せの判者にもなっています。 この和歌は、家隆が七十二歳の時、九条道家の娘・竴子(しゅんし)が、後堀河天皇の中宮として上がる際、その屏風歌を頼まれて詠んだものだと伝えられています。 秋の気配を感じながらも、いまだ夏であることの淡い驚きを素直に詠んでいる、爽やかな歌です。 |
| ◀前の和歌へ 次の和歌へ▶ |