河原左大臣
小倉百人一首 014 |
陸奥の しのぶもぢずり 誰ゆゑに 乱れそめにし 我ならなくに |
| みちのくの しのぶもぢずり たれゆゑに みだれそめにし われならなくに |
河原左大臣 |
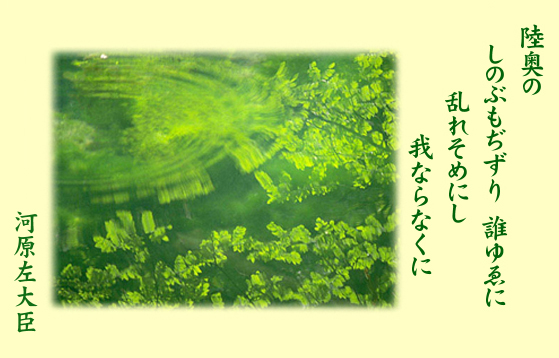 |
| 読み みちのくの しのぶもぢずり たれゆゑに みだれそめにし われならなくに 現代意訳 奥州のしのぶもじずりの乱れ模様のように、私の心も(恋のために)乱れていますが、いったい誰のためにこのように思い乱れているのでしょう。 (きっとあなたの所為に違いありません) ※しのぶもぢずり / 福島県の旧信夫郡あたりで使われていた、乱れ模様に染められた布のこと。 ※ 我ならなくに / 「なく」は打ち消しで、「私ではないのに」の意 季節 - 出典 「古今集」 解説 河原左大臣(かわらのさだいじん・弘仁13年~寛平7年 / 822~895年)は源 融(みなもとのとおる)のことで、元は嵯峨天皇の皇子でしたが、皇族をはなれて源の姓を名乗りました。 貞観十四年(872)に左大臣となり、京都六条の河原院に住んだことから、河原左大臣と呼ばれるようになりました。 融は宇治と嵯峨に別荘を持っていましたが、宇治の邸は融がなくなった後、藤原道長の別荘となり、その子の関白・藤原頼通が寺に改めたのが平等院です。 河原左大臣は、ある日恋人から届いた手紙の返事として、この和歌をつくったと言われていますが、恋に悩む心のうちが目に見えるようです。 「しのぶもぢずり」は忍び草を用いた乱れ模様の布のことで、これによって、心の乱れが目に見える形で詠まれています。 更に、結句の「我ならなくに(私のせいではなく)」によって、和歌に余情をもたせていて、「しのぶもぢずり」も「(恋を)忍ぶ」、「乱れそめにし」も「(恋心に)乱れ」などを想起させ、味わいあるつくりになっています。 |
| ◀前の和歌へ 次の和歌へ▶ |